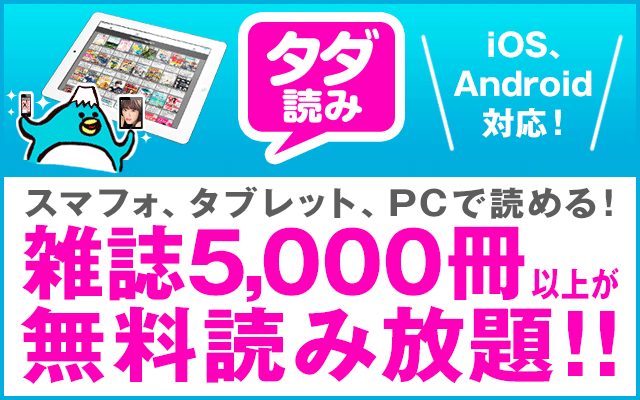暑さも落ち着き、運動を行うには最適な秋の季節がやってきました。涼しいこの季節に自然と体を動かしたくなる方も多いのではないでしょうか。 しかし、普段あまり運動をしていない方は、運動した翌日に疲労感を感じてしまい、運動する習慣が続かないということもあるかと思います。
無理のない範囲で運動をすることに加え、「栄養」と「休養」を意識し体をケアすることが秋の運動を無理なく続けるポイント。 そこで今回は、秋の運動を心地よく続けるために大切な運動後の栄養ケアなどについて、スポーツ栄養士の川端理香さんにお話を伺いました。

川端 理香さん
管理栄養士 元日本オリンピック委員会強化スタッフ
アテネオリンピックでは管理栄養士として選手を栄養面からサポート。その他、サッカー選手やプロ野球、プロゴルフなど3万人以上のアスリートの栄養サポートを行う。
適切な栄養補給で疲労感が溜まりにくい体づくりを
運動後の疲労感をケアし、体の休息を促すためには「何を・いつ食べるか」が重要です。運動後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、体が栄養を効率よく吸収しやすい時間帯。このタイミングで栄養を補給することで、より高いサポートが期待できます。 また、筋トレ後の回復は 24 時間ほど続くため、その後の3食の栄養バランスも大切です。糖質とたんぱく質の摂取バランスは目安として、糖質:たんぱく質=2〜3:1 が理想的とされています。
運動後の体のケアにおすすめの栄養成分

運動によって失われやすい栄養素や、疲れやすい身体におすすめのビタミンなど 「ケア」の視点から栄養を見直すことが、長く快適に運動を続けるには重要です。今回は川端さんに運動後の体のケアにおすすめの栄養成分を聞いています。
①たんぱく質
たんぱく質は筋肉の主要な構成成分であり、運動後の筋繊維の修復に欠かせない栄養素です。また、筋肉に蓄積された疲労物質の分解や代謝を助ける役割も担っており、筋機能の維持に重要な働きを果たします。運動後は筋肉の修復と成長を促すために速やかに補給することが重要です。
たんぱく質は肉・魚・卵・乳製品などの食品から摂取することができ、水分補給もしやすくホエイプロテインの原料でもある牛乳もおすすめ。牛乳には日本人に不足しがちなカルシウムや、疲れた体におすすめのビタミンB₁も含まれています。また、豆腐や納豆などの大豆製品は腸内環境を整える食物繊維も一緒に摂れるため、積極的に取り入れたい食品です。
②ビタミンB1
ビタミンB₁は糖質代謝に不可欠な補酵素であり効率的なエネルギー生成を促進します。これにより、身体のエネルギー不足を防ぎ疲労感の軽減をサポートします。また、神経細胞が正常に働く為にも大切な栄養素であり、糖質の多い食事を摂る方やストレスが強い方は消費が増加するため、適切な補給が必要です。
ビタミンB₁は水に溶けやすく体内に蓄積されにくいため、汗をかく運動時の環境では失われやすい栄養素です。そのため、日常的にバランスの取れた食事を心がけることが大切になります。 また、にんにく、たまねぎなどと一緒に摂取することで吸収率が高まるため「豚キムチ」、「納豆にねぎをのせる」といったメニューはおすすめの調理法です。
③エイコサペンタエン酸(EPA)
EPAは青魚に多く含まれる「オメガ 3 脂肪酸」の一種で、疲労感を抱えた体をサポートするとされています。また、交感神経の活動を調整する可能性がある栄養素とされ、激しい運動やストレスなどによって乱れがちな自律神経のバランスをサポートすることが期待されています。これにより「疲れが取れにくい」といった日常の不調にも働きかけます。
さんま、いわし、ぶりなどに多く含まれるEPAは、赤身部分よりも脂身に多く含まれています。熱、光、酸素に弱く酸化しやすい性質を持っており、加熱によって生活習慣病のリスクを高める過酸化脂質に変化する可能性があるため、刺身などでの摂取がおすすめ。酸化を抑えるためにはビタミンA・C・E などの抗酸化ビタミンと一緒に摂取することをおすすめします。
④イミダペプチド
イミダペプチドは強い抗酸化作用を持ち、体内で発生する活性酸素を除去することで、細胞へのダメージを抑え、疲労感の蓄積を防ぐ働きがあるとされています。
牛肉や豚肉、マグロなどにも含まれていますが、含有量が多いものとして鶏のむね肉が注目されています。コンビニで購入できるサラダチキンからもイミダペプチドを摂取することは可能ですが、 成分が水分として流出する恐れがあるため、スープやカレーなど、水分ごと食べられる料理がおすすめです。
時間栄養学について

従来の栄養学は「何を」「どれだけ」食べるかに着目してきましたが、そこに「いつ食べるか」という視点を加え、体内時計のリズムに合わせて食事をとることで、より効果的に健康の維持や病気の予防を目指すアプローチを「時間栄養学」といいます。
私たちの体内時計は大きく分けて2種類存在します。
① 中枢時計:脳の視交叉上核にあり全身をコントロール。眼の近くにあり朝の日の光でリセットされる。
② 末梢時計:肝臓や腸などの臓器にあり各々リズムを刻んでいる。食事や運動によって調整される。
2 つのリズムを食事タイミングに合わせることで、消化・代謝が効率的に行われ、健康な状態が維持されやすくなります。 一方、朝遅くまで寝ている、朝食を摂らないなど体内時計が乱れるとそれぞれの臓器や組織が持つリズムを狂わせ体調不良が起こってしまうのです。
スポーツを行う人にとっても、食事のタイミングを体内時計に合わせて最適化することで、運動効果を上げるとともに休息や体調管理を効率的に行うことが可能です。
時間帯別アプローチ
・朝の運動(起床後すぐ〜午前中)
朝日を浴びながら運動することで体内時計が整い代謝が高まります。これにより脂肪燃焼や集中力アップが期待できます。また、軽い運動でもセロトニンが分泌されるため、ストレスの軽減にもつながります。運動前には糖質源であるバナナやヨーグルトに果物を加えた軽食などでエネルギー補給を、運動後はたんぱく質と炭水化物を組み合わせた食事がおすすめです。
・夕方・夜の運動(仕事・学校後〜就寝前)
夜の運動は体温や筋肉の柔軟性が高いためケガのリスクが減り、パフォーマンスも上がりやすいのが特徴です。さらに、適度な運動は深い眠りを促します。ただし、激しすぎる運動は逆効果になるため就寝の2〜3時間前までに終えるのがおすすめです。運動前は消化に負担をかけない白米やバナナなどの炭水化物と鶏ささみ、ヨーグルトなどのたんぱく質を摂りましょう。
運動にぴったりの秋の季節。栄養面にも意識を向け、無理なく運動習慣を身につけて健康な生活を送っていきましょう。 WEBサイト「大塚製薬 栄養素カレッジ」では健康と栄養素についての正しい知識づくりをサポートする情報を発信しています。
WEBサイト「大塚製薬 栄養素カレッジ」
URL: https://www.otsuka.co.jp/college