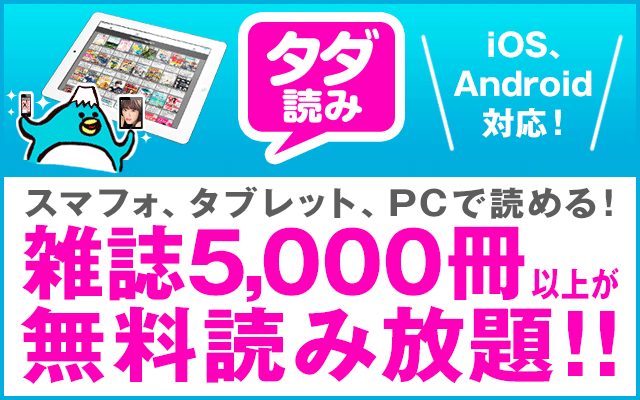株式会社Visionの代表取締役・平⼭智裕⽒は、IT業界で多くのプロジェクトが失敗する背景には、「本当に必要な声を拾えていない」という共通の問題があると語る。Visionは、要件定義や基本設計といった上流⼯程を重視し、プロジェクトの軌道修正を担う存在だ。技術だけでなく⼈との関わりを⼤切にし、地⽅との連携を通じて働く⼈の⼈⽣にも寄り添う。平⼭⽒は、これからのIT現場では「聞く⼒」がプロジェクト成功の鍵を握ると考えている。
うまくいかないプロジェクトの共通点
私はこれまで数多くのプロジェクトに関わってきましたが、最初から最後までスムーズに進んだ案件は決して多くありません。むしろ、途中でうまくいかなくなってから相談を受けるケースがほとんどです。
その多くは、「最初の聞き取り=要件定義」の精度に問題があります。たとえば「使いやすいシステムにしてほしい」という要望はよくありますが、その「使いやすさ」が何を指しているのかを、明確に⾔語化できていないケースがほとんどです。画⾯設計が複雑なのか、動作が遅いのか、あるいは操作フローが煩雑なのか──その⼀つひとつを丁寧に聞く必要があるのです。
しかし多くの企業では、この重要な⼯程を曖昧なまま開発に着⼿してしまいます。その結果、本来であれば最初に修正すべき箇所が⾒過ごされ、リリース後にバグとして表⾯化したり、バージョンアップ時に⼤きな障害となったりします。
私たちVisionが担っているのは、そうした「歪んだプロジェクト」の軌道修正です。システム開発前にお客様としっかり対話を重ね、本当に必要なものを⾒極めていく。これからのIT業界には、こうした「上流⼯程」の重要性を理解し、実践できる企業こそが求められていると強く感じています。

プロジェクト成功の鍵は、「聞く⼒」と1対1の対話
私は、経営においても開発においても、「聞くことの⼤切さ」を常に感じています。Visionでは、社員⼀⼈ひとりと真摯に向き合うことを徹底しており、⽉に⼀度の意⾒交換の場では、プロジェクトの進捗だけでなく、仕事の悩みや個⼈の思いも含めて話し合える雰囲気づくりを⼤切にしています。意⾒交換会の後に開催される飲み会の参加率も90%を越えており、⾃然なコミュニケーションの場として根付いています。
それだけではなく、私はできる限り、社員と1対1で話す時間をつくるようにしています。⼀緒に⾷事をしたり、仕事終わりに少し話したりする中で、会社では⾔いづらいことも素直に話してもらえることが多いのです。
社員数を最⼤50名までに制限しているのも、この「距離感」を⼤切にしたいからです。以前勤めていた会社では、社⻑が社員の名前を覚えていないことに驚きました。私は、全員の名前を覚え、どんな仕事をしているのか、どんな⼈⽣を歩んでいるのかを把握できる規模でありたいと考えています。
会社は「居⼼地のいい場所」であるべきだと考えています。⼈⽣の中で、会社にいる時間は決して短くありません。だからこそ、「会社に⾏くと気持ちが軽くなる」「何かが解決する」──そんな場所でありたいと願っています。

地⽅から広げる、「戻れる場所」という新しい選択肢
地⽅とのつながりは、私にとって⼤きなテーマです。これからの時代、親の介護や家族の事情、ライフスタイルの変化などを理由に、地元へ戻る⼈がますます増えていくと思います。しかし、いざ地元に戻ると、これまで積み重ねてきたスキルや経験が⼗分に活かせない。結果として、アルバイトなどに就かざるを得ない⽅も多く、それは⾮常にもったいないと感じています。
Visionでは、そうした⼈たちが「地元に戻っても働き続けられる」仕組みづくりを進めています。具体的には、まず半年〜1年ほど関東で研修を⾏い、プロジェクトの進め⽅や業務の基礎を学んでもらう。その後は地元に戻り、リモートで仕事を継続する──そんなモデルケースを現在、構築中です。
2025年の秋には、都内と九州‧佐賀県に新たな開発拠点を設置する予定です。拠点探しの中で出会った佐賀県の⽅々との交流は、私にとって⼤きな刺激になりました。現地で3⽇間⾏動を共にし、その地域にかける熱意に⼼を動かされました。「この⼈たちとなら、地⽅でも本当に何かができる」と感じたのです。
地⽅にノウハウを残し、地域とともに育っていく。Visionは、そんな未来を⾒据える企業でありたいと考えています。技術ももちろん⼤切ですが、それを活かすのは「⼈との対話」であり、仕組みも⼤事ですが、最後に物を動かすのは「関わりの⼒」です。これからも、「聞くこと」を原点に、⼈とのつながりを丁寧に育んでいきたいと思います。
【取材協⼒】
株式会社Vision( https://vision-sys.co.jp/)
代表取締役 平⼭智裕(ヒラヤマトモヒロ)